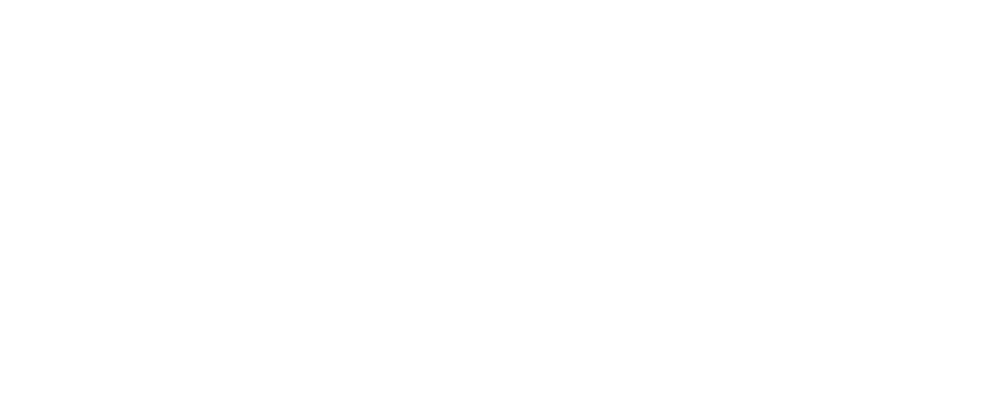2020年01月16日
2020年が始まりました。
今年は東京オリンピックの年です。スポーツを通じて世界平和を訴える年です。
穏やかで平和な一年を願いたいものです。
ただ、8日にイランで旅客機が撃ち落され、大勢の人が亡くなりました。 また、同日にはイラクで米軍基地が攻撃され硝煙が立ち込め、すわ、アメリカとイランとの戦争?との報道も流れ、とても穏やかな年明けとはいきませんでした。
人類史的にはこの100年程の間に、それまでの大英帝国によるパックスブリタニカが衰え、これに代わってアメリカによるパックスアメリカーナが世界の平和を保ってきたと云えますが、最近はアメリカ自らがその役割を降りようとしております。この間隙を縫って中国、ロシアが近隣諸国への覇権争いに熱を上げています。
硝煙の臭いで始まった2020年はこれから更に混沌とする世界への新たな幕開けになるのかもしれません。そうなってほしくはありません。
第二次世界大戦終結から75年、ベトナム戦争終結から45年です。
これらの戦争体験も人類の中で既に風化しているのでしょうか。
考えたくありませんが、そうだとすれば恐ろしいことです。
更にここ数年の地球規模の自然災害は頻度も規模も恐ろしいものがあります。
グレタさんでなくとも声を挙げたくなります。
不安に包まれた2020年の年明けです。ただ、今を生きている自分たちは一人一人がそれぞれの役割の中で落ち着いて未来を信じて進みたいものです。
“ uncertainty and expectation are a joy of the life ”という言葉があります。
英国の経済学者ヒックスの書物にある言葉です。
自分が若い頃、師匠の大塚先生からこの言葉を教えられました
「人間、だれも明日のことはわからない! 確かな事って何もない!でも、その明日を信じ、明日に期待して生きて行こう!だって、それが生きてく喜びじゃない?」
自分はそんな風に勝手に解釈してこれを座右の言葉にしています。
振り返れば、今迄に心が折れたことは何度もありました。そして、その都度この言葉に勇気づけられて今日まで生きてきました。その気持ちは今後も変わりません。
きな臭い年の始まりだからこそ、そして、不安な年の始まりだからこそ、明日を信じ、明日に期待して生きていく覚悟を更に固めて生きたいものです。
2018年01月22日
2018年を迎えました。
毎年、新たな年を迎えるたびに思います、今年も平和で穏やかな一年であってほしいものだと。その気持ちは誰しも同じことです。あちらこちらの神社に訪れた初詣の人々は今年も大勢でした。そして賑やかでした。
初詣の帰りに「お屠蘇」と称して親しい友人と一杯やりました。
今年も平和に!という話が弾んで、ずっと続くこの平和の基は何だ?という話になって、「憲法」だろう、という意見と、いや「日米安全保障条約」だろう、という意見と極端な二極に割れました。
確かにいわゆる「平和憲法」の理念が戦後日本を一貫して戦争から遠ざけてきたと言えるでしょう。それは確かです。一方、現実をみると、海を隔てたすぐ隣にロシア、中国、朝鮮半島と対面しています。どちらの国々も外交と戦争とが表裏で繋がっている容易ではない国々です。理念だけでまともに過ごせるとは決して思えません。
最近、改めて「憲法改正」の話が出ています。日本が置かれた地政学的状況からすれば、70年ほど前の米軍占領下という異常な環境のなかで、米軍将校らによって数週間で原案が作られたという現憲法です。これを現状に照らして見直すという作業は是非必要といえます。少なくとも、これに手を染めてはいけない!といった風潮があることは異常です。「改正」するもどうするも国民が決めることです。国会だけで決められるわけではありません。ジャーナリズムが率先して議論の先鞭をつけるべきところ、その議論すら避ける風潮があることは異常といわざるをえません。自分はそう思います。
憲法といえば聖徳太子の十七条憲法が日本における憲法の嚆矢といっていいでしょう。あまりにも古い話でその真実の程は分かりません。本当に聖徳太子が作ったものなのか?それ自体も疑問が多いとされています。ただ、日本書紀の記述を信ずれば推古十二年(604年)に聖徳太子がこれを作ったとされているようです。
十七条憲法は特に第一条が有名です。「和をもって尊しとなす」というものです。
この十七条憲法はもともと群卿百寮に対するものといえ、いわば諸豪族や諸役人に対する一種の服務規範といったものといえます。
そこに「和をもって・・・」として豪族や役人たちの融和を図っていることが当時の事情をあぶりだしているとも見えます。
ただ、そのあとに「さからうこと無きを宗となす」とあります。
「むさぼりを絶ち欲を捨て(第五条)、いかりを絶ちいかりを棄て(第十条)」
ともあるように穏やかな精神と平静な心を求めていたことが理解できます。為政者にとって、そうしたメンタルを特に必要とした当時の事情がそこから伺えます。
第二条が「篤く三宝を敬え」です。三宝とは仏、法、僧です。
当時大陸からもたらされたばかりの仏教を厚く尊重しています。聖徳太子は勿論のこと、当時の政治権力のトップにいた大臣蘇我馬子も仏教導入の急先方でした。当時の最先端文化と言える仏教の教えを役人たちの服務規範として掲げたところにも、聖徳太子を初めとする当時の人々の新国家創造への熱い思いが伺えます。
ここで最後の条文である第十七条を見てみます。
「大事は独り断ずべからず、必ず衆とともに宜しく論ずべし」
とあります。
ここでようやく実務的な話になってきました。精神的な服務規範だけでなく役人や豪族たちの議論の進め方、仕事の進め方を諭しています。独断で勝手に進めるな!関係する各々の人々とよく話し合って進めなさい、というものです。
非常にわかり易い話です。
似たような文章があります。明治維新の頃、慶応4年3月に明治天皇が掲げたいわゆる「五箇条のご誓文」です。
これが明治政府の基本方針となって明治憲法に反映されているようです。
第一条 「広く会議を興し万機公論に決すべし」
とあります。
「ことに当たって人々の間でよくよく議論して進めなさい!」というものです。
明治憲法も聖徳太子の十七条憲法もその理念とするところは同じです。
話によれば幕末、坂本竜馬が船中で後藤象二郎に語ったといういわゆる船中八策にある「万機宜しく公儀に決すべし」との文言が五箇条のご誓文第一条に反映されているという話も余計な話ですが面白いです。
更に余計な話です。昭和21年の昭和天皇によるいわゆる人間宣言において五箇条のご誓文が全文引用されているようです。明治以来、日本は国体としてこうした民主主義的な考えを持ち続けてきたとの昭和天皇の強い思いからのようです。
それは、明治以来というよりも遥か1400年前の十七条憲法にも見られるように我が国の為政者に綿々と引き継がれてきた国家運営の基本理念、共通認識といっても言い過ぎではありません。
このようなことから、我が国の基本法である憲法を神棚に祭りあげ議論から遠ざけるのではなく、こうした歴史的背景を踏まえた冷静な議論の中で今一度見直されることが望まれます。今はそうした落ち着いた議論が可能な大人の社会になっていると期待したいです。
話があちこちに飛びました。お屠蘇が大分回ってきたようです。
もうすぐ2月です。韓国では平昌オリンピックです。北朝鮮が代表団を送るとかでニュースを賑わしています。事によってはオリンピックの後、世界に大きな波が起きるかもしれません。
穏やかな年は儚い初夢に終わるかもしれません。そうならないよう祈るのみです。
2017年10月27日
「柿食えば 鐘がなるなり 法隆寺」
大食漢といわれた正岡子規はことのほか柿が好きだったようです。
ただ、あの法隆寺を語るにはいささか場違いの感じさえする一句です。
でも、臨場感のある妙にリアルな一句です。
先月、9月下旬に学生時代の友人3人で秋の古都奈良を旅しました。
奈良時代に大陸から伝わったという柿の実は奈良の都に似合います。ところどころで色づいて美味しそうでした。
奈良を旅するのに外せないのが斑鳩の里であり法隆寺です。
法隆寺に代々続く宮大工である西岡常一氏の書物(「木に学べ」小学館)を今一度読み直し、西岡棟梁独特の語り口を反芻しながら法隆寺の建物群を宮大工という視点で改めて見直しました。
さらに、梅原猛氏の書物(「隠された十字架」、「塔」集英社)を読み直し、聖徳太子の霊を閉じ込めたとされる法隆寺をじっくりと、なかでもギリシャからシルクロードを通って伝わったという中門のエンタシスの姿をしみじみと眺めました。
西岡棟梁の家には先祖代々つながる家訓があるそうです。これは文字にはされず代々、次の棟梁となる人に口伝として伝えられてきたものだそうです。
その一つに「堂塔の建立には木を買わず山を買え」というのがあります。木は育った場所によってそれぞれクセがあり、このクセを見抜いて木組みをすることが肝要で、木のクセを知るには山全体を買い、木が育っていた環境に応じて木の特徴を生かして使え!というものです。今では実行できそうもない壮大な発想です。
さらに「百工あれば百念あり これを一つに統ぶるが匠長が器量なり」とあります。
棟梁の使命は多くの職人の心を一つに統ぶることにあり、この使命が果たせない人は棟梁の資格がない。「謹みおそれ匠長の座を去れ」とあります。改めて心すべきリーダーとしての真摯な心構えです。
こうした代々にわたる棟梁たちによって法隆寺は1300年にわたり維持され、引き継がれてきたと言えます。法隆寺が世界文化遺産であるということは、この建物を維持管理してきた、こうした宮大工の人々にもその栄誉が及ぶべきです。
その宮大工の西岡棟梁も既に亡くなりました。棟梁が繰り返し言っていた言葉があります。「技術は進んだが技能は滅んだ」と。これは建築であれ、農業であれ、工場現場であれ等しく言えることです。技術が進むということは反面、現場で考え、工夫し、学ぶという人々の身に着けた技能が重視されないということです。匠の技は要らなくなるということです。
現実の社会事情に照らして已むおえないとはいえ西岡棟梁の嘆きに自分も同感します。
今回の旅の目玉は秋の明日香村をゆったりと巡る事でした。なかでも注目のポイントは明日香村にある甘樫の丘に登る事でした。
甘樫の丘とは645年大化の改新で滅亡した蘇我氏一族の拠点となる場所です。
日本の歴史がようやく記録の上で形になって現れるのは6世紀の頃からでしょう。
継体天皇、欽明天皇の頃と言っていいでしょう。
欽明天皇と深く結びついた蘇我稲目は娘の堅塩媛(きたしひめ)と子姉君(おあねのきみ)を天皇に差出し、堅塩媛は用明天皇と推古天皇を産みます。小姉君は崇峻天皇を産みます。こうして稲目は天皇の外戚となって権力を一層強めます。また、大陸の文化である仏教を受け入れ大臣として権勢を振います。
稲目の息子が蘇我馬子です。
馬子は推古34年(626年)76歳で死したとされますから、稲目をついで大臣になったのは若干20歳そこそこかもしれません。50年以上も大臣の地位にあって、その間、政敵であり仏教導入に反対する物部守屋を誅殺し、娘の河上娘(かわかみのいらつめ)の夫である崇峻天皇を殺害し、仏教を奨めて飛鳥寺を建立し、さらに推古天皇を押し立て、厩戸王子(聖徳太子)を摂政として隋との国交も進めます。
憲法十七条も冠位十二階も教科書等で言われるように、一人聖徳太子だけの実績とは思えません。憲法十七条はいわば役人の服務規程といえます。冠位十二階は司法行政等にかかる人々の身分または職位の定めとも言えます。宮中にかかる重要な定めを摂政である聖徳太子一人が決めたとは思われません。当時、倭国の支配者として絶大な権力を持っていた蘇我馬子も大きく関わっていたと思われます。
馬子の息子が蝦夷であり蝦夷の息子が入鹿です。
蘇我入鹿の代になると蘇我氏一族の運命は一挙に暗転します。「おごれる者は久しからず!」と云います。皇極女帝の寵愛を過信したのかもしれません。入鹿には驕りも生じ、スキもあったことでしょう。入鹿は王族の一人である山背大兄王子一族を罪なくして皆殺しにします。その皆殺しの現場が斑鳩宮であり聖徳太子が建てた旧法隆寺です。古人大兄王子擁立を狙う蘇我一族にとって山背大兄王子は皇位継承に邪魔だからというのが理由とされています。
山背大兄王子殺害は643年のことです。そして起きたのが645年の乙巳の変(大化の改新)です。
当時最高の権力者であった蘇我入鹿が宮中、それも皇極帝の面前で、しかも皇極帝の長男である中大兄皇子によって惨殺された!との報を受けた父親の蝦夷は自らの邸宅、武器庫など甘樫の丘にある建物群一切を焼き自らも生命を絶ちました。
このときに焼失を免れた国記、天皇記などの書物の一部が後日、古事記や日本書紀を記述する際の重要な資料になったと言われます。
古代日本史の上で初めて外交、内政、宗教、文化等あらゆる面で突出した実績を残した蘇我本宗家一族はこうして滅びました。その舞台が甘樫の丘です。
蘇我一族の無念の思いが込められた丘です。
甘樫の丘のすぐ南に石舞台古墳があります。これは後世、誰かによって墓が暴かれたもので、無残にも崩土が削り取られて晒し者のような姿で現在も放置されています。これは蘇我馬子の墓とされています。石舞台古墳に佇んで、その異様な姿に唖然としたものです。誰がどんな目的で行なったものか、なぞは解明されていません。
甘樫の丘に登ると目の前に明日香の里が一望に出来ます。大化の改新惨劇の現場である飛鳥板葺の宮が目の前です。飛鳥川の先には藤原京の跡が望まれます。遠くに聖なる三輪山が見えます。その手前に耳成山が、そして左手目の前に畝傍山が、目を転じて右手には天香久山です。大和三山が見事に見渡せて感激です。後の時代に万葉集で数々の歌に詠まれた山々です。滅び去った蘇我一族の栄華が偲ばれます。蘇我入鹿もこの丘に立って明日香の里を見下ろしながら様々な策を練ったことでしょう。
蘇我入鹿に一族23人を皆殺しにされた山背大兄王子とはあの聖徳太子の長男です。推古天皇の後継ぎと目され、仏教に厚く帰依し、平和を深く望む仁徳の人だったようです。この山背大兄王子一族を殺した人々は聖なる聖徳太子からの怨霊にひどくおびえたことでしょう。この為に建てられた寺が現存する法隆寺であるとの見方があります。
旧法隆寺は670年に焼失したとされています。現在の法隆寺夢殿近くで発掘された若草伽藍がその跡地とされています。では、711年に再建されたという現在の法隆寺は誰が何を祈願して建てられたものか?それがどうもはっきりしません。
ただ、710年には平城京への遷都が行われており、藤原一族の氏寺としての興福寺が建てられています。712年には古事記が完成しています。これらの大事業を遂行したのは藤原不比等です。従って、法隆寺再建も藤原不比等が関わっていないはずはありません。
蘇我入鹿をいわばそそのかして山背大兄王子殺害を策謀し、その上、王子殺害を実行した蘇我入鹿をも殺害し、その入鹿殺害の当事者である中大兄皇子を押し立てて大化の改新に及んだ陰の立役者であり陰の策謀家が中臣鎌足とされています。
鎌足の息子である藤原不比等の一族は、その後栄華を極めながら、その直後に見舞われ続けた絶望的な不幸に、ただただ聖徳太子の怨霊の陰を見て恐れおののいたことでしょう。特に藤原不比等の娘であり文武天皇夫人の宮子、同じく聖武天皇皇后の光明子など女性の皇族たちは太子一族の怨霊を鎮めるためにあらゆる手を尽くしたことでしょう。法隆寺の歴史にはそうした怨霊恐怖の影が色濃く見られます。その証拠といえる数々の記録も見られるようです。
初めて登る甘樫の丘の上で斑鳩の里を遠望しながら、遥か1400年前に繰り広げられた阿修羅の人間模様に改めて思いを馳せました。
2017年10月13日
<文法としての複式簿記>
複式簿記は例の「貸方・借方」とまともに取り組む世界です。基礎的なことは簿記の教科書で学ぶしかありません。
複式簿記では基本的に「仕訳」が既に行われたことが前提とされ、「仕訳伝票」がその後どのような動きをするかという世界です。
貸方・借方はそれぞれ運動の法則があって、勘定科目によって増加したり減少したりします。この結果、それぞれの勘定科目は左右の貸借項目として一表になって表現されます。これが試算表です。そして、貸借の金額は必ず一致します。一致していなければ途中で間違えていることが一目でわかります。簿記の世界におけるこのような「貸借均衡の美」がまさに人類の優れた発明の所産といわれるゆえんです。
試算表が出来れば半ば完成です。これを貸借対照表と損益計算書に区分表示します。即ち、決算書が出来ます。ここに至るプロセスがいわば複式簿記の世界です。
即ち、複式簿記は「仕訳」の結果を受けて貸方・借方の法則に則って試算表にまで計算するための法則であり、会計の計算ルールです。いわば、会計における「文法」の世界です。
今では、実務的には殆どパソコンソフトで自動的に計算されています。簿記を知らない人でもパターンを教えられて伝票を入力すれば試算表まで自動計算されます。従って、この「文法」そのものを改めて検討することは実務の世界では極めてまれと言えます。
いわば、与件として会計の世界に与えられた「人類の財産」と言えるからです。
<利害関係者と決算書>
会計は人に利用されて初めて価値があります。利用されるために人々が発明したものです。今では多くの人々が利用し、経済活動での最も重要なツールの一つとして活用されています。
一枚の決算書にしても見る人の立場によって見方が異なります。
株主であればより多くの安定した配当金に関心が向きます。債権者であれば債権の回収に関心が向きます。経営者は株主にも、債権者にも、どちらに向けてもより多くの利益が安定的に欲しいものです。逆に、税務署向けには課税利益が少ない方を望むでしょうし、労働組合には賞与アップの口実となる多額の利益は避けたいところです。
経営者はこれらの利害関係者にそれぞれいい顔をしたいのが人情です。従って、極端に多くの利益が一度に出ても歓迎は出来ませんし、勿論、赤字決算は何としても避けたいところです。
決算書は経営者のこうした心の葛藤の中に存在し続けます。
実は、銀行用、税務署用、自分用、等3通りもの異なった決算書を用意していた経営者に以前お目に掛かったことがあります。こうなると会計を利用した詐欺行為にもなりかねません。また、それほど会計の結果は影響が大きいと言えます。
<経営者の会計>
もともと会計は事業活動の結果を金額として纏めて現状を把握し、それを基に今後の経営に資するべくできたものです。関係ある人々は当然にこれを利用します。しかも、人々は立場によって様々に反応します。関係ある人々とはいわば「利害関係者」です。
従って、会計は常に「利害関係者」の注目の中で実施されています。利害関係者の顔を想像しながら会計が行われます。おのずから経営者は許される限り政治的な配慮をすることになります。会計が「政治の虜」と言われるのはそうした状況にあるからです。
今期はどうしても「利益」を出したい事情にある経営者であれば必要にして妥当な「減価償却」を控えることもあり得ます。陳腐化して処分するしかない在庫品が旧来の帳簿価格のままで計上されていても見て見ぬふりで決算を〆ることもあります。
逆に、商品の販売政策により5年で原価を回収したい強気の経営者は、通常10年の耐用年数とされる新設機械設備を5年の耐用年数で減価償却を行い、早期の回収を図るかもしれません。
化粧品の商品サイクルは短いと言います。新商品のための製造設備も商品サイクルに合わせて減価償却し資金回収を図るという経営判断が必要となります。
たとえば、5千万円する設備をいわゆる一般的な法定耐用年数12年で償却するとします。12年の定率法による償却率は0,208です。償却額は10、400千円です。
一方、当該商品の推定商品サイクルを3年以内と判断すれば3年で償却してしまうという経営判断もありえます。3年の定率法償却率は0,833です、即ち、償却額は41,650千円です。
耐用年数一つとっても、経営者の経営判断の差が現れます。経営判断に応じて会計の計算が行われます。この事例でも償却費の計算だけで31,250千円の差が生じます。
3年で償却するとすれば41,650千円という多額の償却費をカバーするだけの利益を出さなければなりません。そのための経営計画が必要となります。そのための販売戦略が必要となります。
勿論、税務の計算は別です。税務計算はいわゆる法定耐用年数で計算しなければなりません。従って、3年で償却した場合は税務上では31,250千円の所得を加算して税金計算することになります。
<会計表現は経営表現>
経営者の交代で、新任の経営者は前任者が残した大量の不良品、陳腐化品を一挙に処分して多額の赤字をだし、前任者時代の経営と決別を図ることもままあることです。
経営者が当該商品を「陳腐化品」と認めるかどうかがその会社の経営政策であり経営者の経営判断です。「陳腐化品」と認定されればその商品の帳簿価格は時価相当額に変更されることになります。当然に損益計算書には多額の評価減額が計上されることにもなります。
経営者にも現場の人にも「捨てるにはもったいない」という気持ちは常にあります。
しかしスリムな会社を目指す経営者は陳腐化品をそのまま会社の資産として計上しておくことは経営方針に反します。このような場合に会計上は陳腐化品として処分価額たとえば1円まで帳簿を減額し、一方、商品現物は貯蔵品として現物管理するといった
処理方法もありえます。
会計方針は経営方針に従います。会計表現は即ち経営者の経営表現そのものといっていいでしょう。
<黒字倒産の話>
「儲かっているのか?」
経営者であればだれしも「儲かっているかどうか?」が気になるところです。そして、儲かっているかどうか?を端的に知る手段は決算書で「利益」が出ているかどうか?を見ることです。「利益」とは一年間という期間を区切った時に見える計算上の利益の事です。一方、事業は何年にもわたって継続しています。そこで会計では様々な方法で計算仮定を置いて「利益」を算出します。即ち、決算書の「利益」は様々な計算仮定を置いたうえでの計算上の数値です。そこに思わぬ落とし穴もあります。
「黒字倒産!」
よく聞く言葉です。決算書では黒字になっているのに、即ち「利益」が出ているのに倒産するということです。世間ではよくあることです。
その原因の多くは「利益」と「おカネ」は同じではないということです。「利益」があれば会社は倒産しないか?と言われればそれは「否!」です。
会計上の「利益」は事業活動で動いている「おカネ」を計算仮定に基づいて会計用語に翻譯した結果としての数値です。従って、「おカネ」の姿をそのままに評したものではありません。
会社では「利益」は無くとも「おカネ」があれば倒産することはありません。
どの会社も苦労するのは「資金繰り」です。おカネの入金と出金とのバランスを取る事です。入金に合わせて出金し、出金に合わせて入金することです。
「資金繰りとは時間繰りだよ!」
かつて尊敬する経理のベテラン役員が言った言葉です。
確かにおカネは循環しているのですが支払いに合わせて入金を対応させなければなりません。この「資金繰り」が極めて重要な仕事です。計算上はおカネが足りているのに手許になければ支払いが出来ません。これが「黒字倒産」の原因です。
単純な計算例で見てみます。
Ⅹ社の損益計算書は次のとおりです。10の利益が出ています。しかしおカネが足りません。
損益計算書
売上高 100
仕入高 ―)70
給与 ―)10
経費 ―)10
利益 10
資金繰計算書
利益 10
減価償却費 +) 2
売掛金 -)30
設備費 -)10
借入金 +)10
手元資金 -)18
資金繰計算書では18の資金不足です。この原因は売上高100が全て入金しているわけではなく30が売掛金として来月もしくは再来月に入金するものだからです。従って少なくとも18は資金調達に走らなければなりません。
経営者は損益計算書の利益を見ているだけでは足りません。「勘定あって銭足らず!」ということになります。経営者にとっては損益計算書と同じかもしくはそれ以上に「おカネ」をチェックすべく「資金繰計算書」が重要な資料となります。
<健全経営のための貸借対照表>
忙しい経営者は往々にして損益計算書に目が向きがちです。損益計算書にある「利益」の額に目が行きがちです。それはそれで尤もなことです。
ただ、それだけでは片手落ちといえます。「おカネ!」という視点で経営を見る目を持っていることが必要です。
貸借対照表がこの目を持たせてくれます。簡単な貸借対照表で見てみます。
貸 借 対 照 表
現金 30 買掛金 20
売掛金 30 借入金 70
棚卸資産 40 資本金 40
固定資産 50 剰余金 20
この貸借対照表では売掛金が30、棚卸資産が40あります。これらは現金と同等の会社の資産です。借入金70は売掛金30と棚卸資産40のための借入とも言えます。
売掛金は回収できるのか、棚卸資産は通常値段ですぐ売れるのか、現金化できるのか。
貸借対照表の資産項目については会社の経営に必要な内容かどうかを常にチェックしておく必要があります。会社の資産内容をスリムにしておくことはおカネの無駄を省く経営にはぜひとも必要なことです。
貸借対照表はこの目を持たせてくれます。
経営者は「利益!」だけでなく貸借対照表の中身にも精通していることが必要です。
<結果としての利益>
「利益は目的ではなく結果である!」
これはある創業経営者の言葉です。立派な見識を持った言葉です。
利益を「目的」と見るのと「結果」と見るのとでは大きな違いがあります。
利益を「目的」と見れば「数字としての利益の額」を求める余り目先の数字を作り出すための活動に走りがちです。この結果、経理操作の誘惑に負けて実体のない「仕訳」が行われがちです。東芝の「チャレンジ」の結果が証明しています。
逆に利益を事業活動の「結果」と見れば、その「目的」はその会社本来の事業目的をひたすら追求することであり、その事業が求めるミッションの追求になります。結果としてその会社の進むべき方向性がより明確化されます。
長期的に見れば目先の「目的としての利益」を求めるのではなく、本来の事業活動を追求した「結果としての利益」を求めることが将来のより大きな利益をもたらすことは明らかです。
「目標利益」という言葉が実務ではよく言われます。これはあくまでも本来の事業活動を進めた結果として数字的に収斂された「結果としての利益」であるはずです。達成すべき「目的としての数値」ではないはずです。
ただ、「目標利益」が達成できなかったら自分たちの立場がなくなる!といった状況に追い込まれれば「結果としての利益」などと言ってはおられません。なりふり構わず「利益という数字」を積み上げるため狂奔することになります。その先の末路は暗闇です。東芝の悲劇がこれを証明しています。
<経営の要としての会計>
企業であれNPO法人であれ公共団体であれ、組織としておカネが動くところ会計があります。ただ、どこの事業においても会計の機能は主役ではありません。派手ではなく、目立つこともありません。でも、なくてはならない機能であり重要な機能です。
製造、販売、などの部門は事業の中での基幹部門であり、重要であることは勿論ですが、会計の部門はこれらの基幹部門とは少し異質です。
会計伝票はおカネが動くところ事業のあらゆるポジションから会計部門に集まってきます。注意すればどこの部門でどのようなおカネがどれだけ動いているか即座に把握できます。経常的なおカネかそうでないおカネかも見当がつきます。
事業の中のおカネの動きを注視することでどこのポジションで何が起きているかも推察できます。
製造部門であれ、販売部門であれ、資材部門であれ、おカネという切り口であらゆる部門の出来事を見通すことが出来ます。これが他の部門にはない会計部門独特の機能です。会計という言語は事業共通の言語だからです。そして、各部門から集まった情報を経営にどう生かすかが会計部門で生きる人々の働き甲斐となります。
この意味で会計部門は経営の要としての機能を持つといっていいでしょう。ただ、それは見る目を持つ人にこそいえることで、見ようとしない人には見えません。
数字を集計するだけが経理マンの仕事ではありません。そんな経理マンは要りません。
数字の背景にあるヒトの動きが見えて初めて経理マンとしての存在意味があり、会計の面白さがわかるといえます。
将に、会計伝票からヒトが見えます。そして決算書から経営が見えます。
2017年10月12日
<会計は事業の言語である!>
「会計は事業の言語である」といわれます。確かに業種や規模等に関わらず、また、国の如何を問わず、その会社の決算書を見れば会社の事業活動の結果が理解できるからです。それは、決算書が全ての事業に共通する「会計という言語形式」を持つからです。
即ち、会社の膨大な事業取引を会計の言語である「勘定科目」という単語に翻訳し、複式簿記という文法でもって整理統合し、決算書という報告様式で表現します。この意味で会計はビジネス社会の共通言語であるといえます。
ただ、「会計は事業の言語である」との言葉の中身は会計がビジネス社会の共通言語であるという意味だけではありません。
ではどういう意味なのでしょう。
横浜市立大学名誉教授の青柳文司先生は早くから「会計は言語である」との見方で研究されています。「会計」そのものが一種の言語活動であるとの見方によるものです。
その考えの一端を拝借して会計の世界を「記号論」の見方で考えてみます。
<記号と会計>
人間は記号を使用する動物です。記号を通じて考え、記号を見てその次に来る事態を予測し、反応し、準備します。記号によって人間関係を維持し、記号を解釈して人間社会が成り立っています。
現実に札束を見なくても預金通帳の残高を見ておカネの在り高が理解できるわけです。通帳の預金残高は札束を対象とする記号です。更に札束も記号です。これで何が買えるのかが予測できます。
ただ、人間の育った環境、歴史、文化などによって記号を見ての反応、予測、準備の仕方は異なります。記号を解釈する人によって記号に含まれる意味の捉え方が異なるからです。
会計は事業の膨大な取引を勘定科目という会計の言葉に翻譯すると言いました。ここで翻訳された勘定科目は事業取引を記号化したものです。記号化された事業取引が組織的・統一的に整理されて決算書になる訳です。そして事業内外の人々は記号化された事業体の姿を見て何かを予測し、反応します。そこに決算書を巡る人々の阿鼻叫喚の世界があります。
<記号論>
確かに会計を一種の記号活動の一形態と見る見方があります。会計を記号活動として見たらどういうことがいえるのでしょう。
記号に関する研究分野を記号論といいます。
記号論には意味論、構文論、語用論の三つの分野があります。
- 意味論とは記号とその記号が意味する内容に関する研究分野です。会計の世界では「仕訳」の世界がこれに相当します。
- 構文論とは記号と記号の関係に関する研究分野です。記号に働く文法などの世界であり、会計の世界では複式簿記の法則に関する世界です。
- 語用論とは記号とその記号を利用する人間との関連を研究する分野です。会計の世界では決算書とその利用者たちの予測、反応、準備、行動等に関わる世界です。
「会計」を「記号活動の世界」として見ると、会計における「仕訳」及び「複式簿記」並びに「会計を巡る人々」の位置関係がよりよく理解できます。
記号論では意味論の世界が特に発達しています。「意味とは何か?」からスタートです。会計の世界では「仕訳」が出発点となります。
<会計の生命は「仕訳」にある>
会計は「勘定科目」と「金額」という記号で対象を表現します、また、「勘定科目」という単語は限られた数しかありません。膨大な事業取引を限られた数の単語に翻譯しなければなりません。これが会計における「仕訳」の世界です。
会計学の世界は棚卸資産会計、固定資産会計、売上高計上基準、引当金計上基準等々いわゆる会計方法論の勉強が盛んです。大学の授業も会計士試験も会計学の勉強といえばこれらを学ぶことが中心です。これは翻訳すべき対象である企業の出来事をいかに的確に会計という言語に翻譯するかという、いわば翻訳技術の勉強といっていいでしょう。
ただ、会計理論を学んだからといって適切に会計が出来るとはいい切れません。それ以前に、翻譯される対象である事業の取引実態をしっかり理解できていなければ翻訳そのものがおぼつかないでしょう。また、翻訳にあたっての実務慣習などに精通していないと適切な翻訳は困難です。
この意味で会計の生命はいかに適切に生きた「仕訳」が出来るか否かにあるといっていいでしょう。
<「仕訳」の世界>
例えば損益計算書に「旅費交通費」という費用項目があります。ここで言う「旅費交通費」とはいわゆる一般用語ではありません。勘定科目としての「旅費交通費勘定」といういわば会計の専門用語としての単語です。
これがどのように違うのか少し見てみましょう。
- 仕事で出張して新幹線の切符代を精算した・・・・「旅費交通費」
- 通勤定期代を支払った・・・・・・・・・・「給与―通勤手当―」
- 客の接待でタクシー代を払った・・・・・・・・・・・「交際費」
- タクシーのチケットをあらかじめ買い置きした・・・・「仮払金」
- 出張のホテル代を支払った・・・・・・・・・・・「旅費交通費」
同じように見える交通に関わる費用であってもその内容によって様々な勘定科目に区分されます。どのような内容であるのかを十分に理解しなくては適切な翻訳にはなりません。
このことは「売上高」であっても「仕入高」であっても同じことがいえます。どのような勘定科目であっても同じことです。
事業体の中では常にモノが動きヒトが動き情報が動いています。これをどのタイミングでどのような金額で、どんな勘定科目で翻訳するのか?これが会計の出発点であり会計の生命線がここにあるといっていいでしょう。
<取引と仕訳の世界>
1、「売上高」をいつ認識し計上するかは常に問題となりやすいところです。
一般に売上高の認識時点は「出荷基準」といわれて製品等が客先に向けて出荷 された時点で「売上高」として計上されます。ただ、例外もあります。
営業部門は当年度の売上高予算があります。どうしてもこれを達成したい時、客先と合意して当社倉庫に在庫したまま客先の了解の基、売上高に計上することもあります。「預かり売上」などとも呼びます。この場合には例外を正当化するべく客先が当該製品を引き取ったとの確認が必要です。従って、客先からの「預け証」の入手、こちらからの「預かり証」の発行などは最低限揃えておく必要があります。
即ち、少なくとも客先が「買った」、こちらが「売った」という証拠を揃えて おく必要があります。
「売上高」という会計の言葉に翻譯するにはその会社で定められた内部手続きをクリアーしなければなりません。この内部手続きを一般に「内部統制制度」といいます。
従って、適切に会計が行われるためには適切な内部統制制度が社内で確立して いることが大前提となります。
公認会計士等が行う会計監査の主な仕事はこの内部統制制度がしっかりしているかどうか?現実に機能しているかどうかを確かめることが大きな仕事となっています。
2、 完成品が出来るまでには様々な工程があります。最終製品となる前に一部の加工工程が必要なことがあります。この際に特定の加工工程を外部に発注する事があります。
A社はいわゆる外注による取引形態です。外注先にある半製品はA社の在庫品であり外注加工に掛かる費用は外注費という製造費用となります。
一方、B社のように半製品を加工先に売却して、加工された品物を改めて購入するという取引形態があります。売却された半製品は相手先に管理責任があるということになります。
A社、B社ともに似かよった加工工程ですが取引形態が異なれば会計も違ってきます。どちらが正しいかではなく、その会社にとってはどちらが管理しやすいかの問題です。
外注という取引形態をとるA社に比べ外注先に移動した半製品を売上高として計上するB社はA社に比べて売上高も仕入高も増加します。
場合によってはB社の場合、「売上高」という数字を求める余り、外注先に半製品を押し込んで「売上高」をかさ上げすることが容易にできるかもしれません。
会計の仕訳は取引形態によっても変わるものです。当然に取引の実態を理解しなければ適切な仕訳は出来ません。
<会計方針と経営方針>
東芝では「不適切」な会計が基で大変なことになっています。トップ経営者が「チャレンジ」と称して無理に売上高を増加させ、結果として数日間で数百億円と言う利益の水増しを行ったという事件です。バイセル取引というそうです。
取引実態が適切とはいえない取引であれば翻訳された会計の世界も当然に不適切となります。
製品在庫を不当に水増しして会計に表現すれば当然に会計は「粉飾決算」となります。こうした操作は最も初歩的な粉飾事例であり、今までに沢山すぎるほどの事例があります。
経済取引そのものが不正な取引であればこれを翻訳した会計の世界も当然に不正なものとなります。翻訳作業がどんなに正しくても経済取引そのものが正しくなければ当然に非難されます。それが会計の辛いところであり会計の限界と言えます。
どんな企業であれ会計ルールの選択は会計方針に左右されます。そして会計方針は結局のところ経営者の経営方針に従わざるを得ないからです。
従って、適切な「仕訳」が出来るためには、適切な会計方針が必要であり、また、そのためには適切な経営方針が前提となる道理です。
<対象をチャンと見ること>
会計の生命は「仕訳」にあると言いました。対象を適切に翻訳し、会計の世界に反映するためには先ず、現実の取引が行われている現場の姿をチャンと見なければなりません。チャンと見るためには現場の人々から素直に聞くことです。先入観なく現場をチャンと見ることです。そのことが出来なければまともな会計は出来ません。
経理を行う人は机に座っているばかりではダメだということです。経理伝票の基となる現場に詳しく精通していなければダメだということです。
絵を描くとき最も注意すべきことは対象をよりチャンと見ることです。自分も昔、習っていた絵の先生から「もっとよく見なさい!」と何度も何度も注意されました。自分ではしっかり見ているつもりでも見えていないことが多いのです。
心の先入観が目の視力を奪ってしまうのかもしれません。
会計の世界でも同じことです。
「人は自分が見たいと思うものしか見ていない」とはローマの英雄カエサルの言葉とされています。
「見る」ということは単純なことですが意外と難しいことなのかもしれません。
<会計は事業の言語である!>
「会計は事業の言語である」といわれます。確かに業種や規模等に関わらず、また、国の如何を問わず、その会社の決算書を見れば会社の事業活動の結果が理解できるからです。それは、決算書が全ての事業に共通する「会計という言語形式」を持つからです。
即ち、会社の膨大な事業取引を会計の言語である「勘定科目」という単語に翻訳し、複式簿記という文法でもって整理統合し、決算書という報告様式で表現します。この意味で会計はビジネス社会の共通言語であるといえます。
ただ、「会計は事業の言語である」との言葉の中身は会計がビジネス社会の共通言語であるという意味だけではありません。
ではどういう意味なのでしょう。
横浜市立大学名誉教授の青柳文司先生は早くから「会計は言語である」との見方で研究されています。「会計」そのものが一種の言語活動であるとの見方によるものです。
その考えの一端を拝借して会計の世界を「記号論」の見方で考えてみます。
<記号と会計>
人間は記号を使用する動物です。記号を通じて考え、記号を見てその次に来る事態を予測し、反応し、準備します。記号によって人間関係を維持し、記号を解釈して人間社会が成り立っています。
現実に札束を見なくても預金通帳の残高を見ておカネの在り高が理解できるわけです。通帳の預金残高は札束を対象とする記号です。更に札束も記号です。これで何が買えるのかが予測できます。
ただ、人間の育った環境、歴史、文化などによって記号を見ての反応、予測、準備の仕方は異なります。記号を解釈する人によって記号に含まれる意味の捉え方が異なるからです。
会計は事業の膨大な取引を勘定科目という会計の言葉に翻譯すると言いました。ここで翻訳された勘定科目は事業取引を記号化したものです。記号化された事業取引が組織的・統一的に整理されて決算書になる訳です。そして事業内外の人々は記号化された事業体の姿を見て何かを予測し、反応します。そこに決算書を巡る人々の阿鼻叫喚の世界があります。
<記号論>
確かに会計を一種の記号活動の一形態と見る見方があります。会計を記号活動として見たらどういうことがいえるのでしょう。
記号に関する研究分野を記号論といいます。
記号論には意味論、構文論、語用論の三つの分野があります。
- 意味論とは記号とその記号が意味する内容に関する研究分野です。会計の世界では「仕訳」の世界がこれに相当します。
- 構文論とは記号と記号の関係に関する研究分野です。記号に働く文法などの世界であり、会計の世界では複式簿記の法則に関する世界です。
- 語用論とは記号とその記号を利用する人間との関連を研究する分野です。会計の世界では決算書とその利用者たちの予測、反応、準備、行動等に関わる世界です。
「会計」を「記号活動の世界」として見ると、会計における「仕訳」及び「複式簿記」並びに「会計を巡る人々」の位置関係がよりよく理解できます。
記号論では意味論の世界が特に発達しています。「意味とは何か?」からスタートです。会計の世界では「仕訳」が出発点となります。
<会計の生命は「仕訳」にある>
会計は「勘定科目」と「金額」という記号で対象を表現します、また、「勘定科目」という単語は限られた数しかありません。膨大な事業取引を限られた数の単語に翻譯しなければなりません。これが会計における「仕訳」の世界です。
会計学の世界は棚卸資産会計、固定資産会計、売上高計上基準、引当金計上基準等々いわゆる会計方法論の勉強が盛んです。大学の授業も会計士試験も会計学の勉強といえばこれらを学ぶことが中心です。これは翻訳すべき対象である企業の出来事をいかに的確に会計という言語に翻譯するかという、いわば翻訳技術の勉強といっていいでしょう。
ただ、会計理論を学んだからといって適切に会計が出来るとはいい切れません。それ以前に、翻譯される対象である事業の取引実態をしっかり理解できていなければ翻訳そのものがおぼつかないでしょう。また、翻訳にあたっての実務慣習などに精通していないと適切な翻訳は困難です。
この意味で会計の生命はいかに適切に生きた「仕訳」が出来るか否かにあるといっていいでしょう。
<「仕訳」の世界>
例えば損益計算書に「旅費交通費」という費用項目があります。ここで言う「旅費交通費」とはいわゆる一般用語ではありません。勘定科目としての「旅費交通費勘定」といういわば会計の専門用語としての単語です。
これがどのように違うのか少し見てみましょう。
- 仕事で出張して新幹線の切符代を精算した・・・・「旅費交通費」
- 通勤定期代を支払った・・・・・・・・・・「給与―通勤手当―」
- 客の接待でタクシー代を払った・・・・・・・・・・・「交際費」
- タクシーのチケットをあらかじめ買い置きした・・・・「仮払金」
- 出張のホテル代を支払った・・・・・・・・・・・「旅費交通費」
同じように見える交通に関わる費用であってもその内容によって様々な勘定科目に区分されます。どのような内容であるのかを十分に理解しなくては適切な翻訳にはなりません。
このことは「売上高」であっても「仕入高」であっても同じことがいえます。どのような勘定科目であっても同じことです。
事業体の中では常にモノが動きヒトが動き情報が動いています。これをどのタイミングでどのような金額で、どんな勘定科目で翻訳するのか?これが会計の出発点であり会計の生命線がここにあるといっていいでしょう。
<取引と仕訳の世界>
1、「売上高」をいつ認識し計上するかは常に問題となりやすいところです。
一般に売上高の認識時点は「出荷基準」といわれて製品等が客先に向けて出荷 された時点で「売上高」として計上されます。ただ、例外もあります。
営業部門は当年度の売上高予算があります。どうしてもこれを達成したい時、客先と合意して当社倉庫に在庫したまま客先の了解の基、売上高に計上することもあります。「預かり売上」などとも呼びます。この場合には例外を正当化するべく客先が当該製品を引き取ったとの確認が必要です。従って、客先からの「預け証」の入手、こちらからの「預かり証」の発行などは最低限揃えておく必要があります。
即ち、少なくとも客先が「買った」、こちらが「売った」という証拠を揃えて おく必要があります。
「売上高」という会計の言葉に翻譯するにはその会社で定められた内部手続きをクリアーしなければなりません。この内部手続きを一般に「内部統制制度」といいます。
従って、適切に会計が行われるためには適切な内部統制制度が社内で確立して いることが大前提となります。
公認会計士等が行う会計監査の主な仕事はこの内部統制制度がしっかりしているかどうか?現実に機能しているかどうかを確かめることが大きな仕事となっています。
2、 完成品が出来るまでには様々な工程があります。最終製品となる前に一部の加工工程が必要なことがあります。この際に特定の加工工程を外部に発注する事があります。
A社はいわゆる外注による取引形態です。外注先にある半製品はA社の在庫品であり外注加工に掛かる費用は外注費という製造費用となります。
一方、B社のように半製品を加工先に売却して、加工された品物を改めて購入するという取引形態があります。売却された半製品は相手先に管理責任があるということになります。
A社、B社ともに似かよった加工工程ですが取引形態が異なれば会計も違ってきます。どちらが正しいかではなく、その会社にとってはどちらが管理しやすいかの問題です。
外注という取引形態をとるA社に比べ外注先に移動した半製品を売上高として計上するB社はA社に比べて売上高も仕入高も増加します。
場合によってはB社の場合、「売上高」という数字を求める余り、外注先に半製品を押し込んで「売上高」をかさ上げすることが容易にできるかもしれません。
会計の仕訳は取引形態によっても変わるものです。当然に取引の実態を理解しなければ適切な仕訳は出来ません。
<会計方針と経営方針>
東芝では「不適切」な会計が基で大変なことになっています。トップ経営者が「チャレンジ」と称して無理に売上高を増加させ、結果として数日間で数百億円と言う利益の水増しを行ったという事件です。バイセル取引というそうです。
取引実態が適切とはいえない取引であれば翻訳された会計の世界も当然に不適切となります。
製品在庫を不当に水増しして会計に表現すれば当然に会計は「粉飾決算」となります。こうした操作は最も初歩的な粉飾事例であり、今までに沢山すぎるほどの事例があります。
経済取引そのものが不正な取引であればこれを翻訳した会計の世界も当然に不正なものとなります。翻訳作業がどんなに正しくても経済取引そのものが正しくなければ当然に非難されます。それが会計の辛いところであり会計の限界と言えます。
どんな企業であれ会計ルールの選択は会計方針に左右されます。そして会計方針は結局のところ経営者の経営方針に従わざるを得ないからです。
従って、適切な「仕訳」が出来るためには、適切な会計方針が必要であり、また、そのためには適切な経営方針が前提となる道理です。
<対象をチャンと見ること>
会計の生命は「仕訳」にあると言いました。対象を適切に翻訳し、会計の世界に反映するためには先ず、現実の取引が行われている現場の姿をチャンと見なければなりません。チャンと見るためには現場の人々から素直に聞くことです。先入観なく現場をチャンと見ることです。そのことが出来なければまともな会計は出来ません。
経理を行う人は机に座っているばかりではダメだということです。経理伝票の基となる現場に詳しく精通していなければダメだということです。
絵を描くとき最も注意すべきことは対象をよりチャンと見ることです。自分も昔、習っていた絵の先生から「もっとよく見なさい!」と何度も何度も注意されました。自分ではしっかり見ているつもりでも見えていないことが多いのです。
心の先入観が目の視力を奪ってしまうのかもしれません。
会計の世界でも同じことです。
「人は自分が見たいと思うものしか見ていない」とはローマの英雄カエサルの言葉とされています。
「見る」ということは単純なことですが意外と難しいことなのかもしれません。
<会計は事業の言語である!>
「会計は事業の言語である」といわれます。確かに業種や規模等に関わらず、また、国の如何を問わず、その会社の決算書を見れば会社の事業活動の結果が理解できるからです。それは、決算書が全ての事業に共通する「会計という言語形式」を持つからです。
即ち、会社の膨大な事業取引を会計の言語である「勘定科目」という単語に翻訳し、複式簿記という文法でもって整理統合し、決算書という報告様式で表現します。この意味で会計はビジネス社会の共通言語であるといえます。
ただ、「会計は事業の言語である」との言葉の中身は会計がビジネス社会の共通言語であるという意味だけではありません。
ではどういう意味なのでしょう。
横浜市立大学名誉教授の青柳文司先生は早くから「会計は言語である」との見方で研究されています。「会計」そのものが一種の言語活動であるとの見方によるものです。
その考えの一端を拝借して会計の世界を「記号論」の見方で考えてみます。
<記号と会計>
人間は記号を使用する動物です。記号を通じて考え、記号を見てその次に来る事態を予測し、反応し、準備します。記号によって人間関係を維持し、記号を解釈して人間社会が成り立っています。
現実に札束を見なくても預金通帳の残高を見ておカネの在り高が理解できるわけです。通帳の預金残高は札束を対象とする記号です。更に札束も記号です。これで何が買えるのかが予測できます。
ただ、人間の育った環境、歴史、文化などによって記号を見ての反応、予測、準備の仕方は異なります。記号を解釈する人によって記号に含まれる意味の捉え方が異なるからです。
会計は事業の膨大な取引を勘定科目という会計の言葉に翻譯すると言いました。ここで翻訳された勘定科目は事業取引を記号化したものです。記号化された事業取引が組織的・統一的に整理されて決算書になる訳です。そして事業内外の人々は記号化された事業体の姿を見て何かを予測し、反応します。そこに決算書を巡る人々の阿鼻叫喚の世界があります。
<記号論>
確かに会計を一種の記号活動の一形態と見る見方があります。会計を記号活動として見たらどういうことがいえるのでしょう。
記号に関する研究分野を記号論といいます。
記号論には意味論、構文論、語用論の三つの分野があります。
- 意味論とは記号とその記号が意味する内容に関する研究分野です。会計の世界では「仕訳」の世界がこれに相当します。
- 構文論とは記号と記号の関係に関する研究分野です。記号に働く文法などの世界であり、会計の世界では複式簿記の法則に関する世界です。
- 語用論とは記号とその記号を利用する人間との関連を研究する分野です。会計の世界では決算書とその利用者たちの予測、反応、準備、行動等に関わる世界です。
「会計」を「記号活動の世界」として見ると、会計における「仕訳」及び「複式簿記」並びに「会計を巡る人々」の位置関係がよりよく理解できます。
記号論では意味論の世界が特に発達しています。「意味とは何か?」からスタートです。会計の世界では「仕訳」が出発点となります。
<会計の生命は「仕訳」にある>
会計は「勘定科目」と「金額」という記号で対象を表現します、また、「勘定科目」という単語は限られた数しかありません。膨大な事業取引を限られた数の単語に翻譯しなければなりません。これが会計における「仕訳」の世界です。
会計学の世界は棚卸資産会計、固定資産会計、売上高計上基準、引当金計上基準等々いわゆる会計方法論の勉強が盛んです。大学の授業も会計士試験も会計学の勉強といえばこれらを学ぶことが中心です。これは翻訳すべき対象である企業の出来事をいかに的確に会計という言語に翻譯するかという、いわば翻訳技術の勉強といっていいでしょう。
ただ、会計理論を学んだからといって適切に会計が出来るとはいい切れません。それ以前に、翻譯される対象である事業の取引実態をしっかり理解できていなければ翻訳そのものがおぼつかないでしょう。また、翻訳にあたっての実務慣習などに精通していないと適切な翻訳は困難です。
この意味で会計の生命はいかに適切に生きた「仕訳」が出来るか否かにあるといっていいでしょう。
<「仕訳」の世界>
例えば損益計算書に「旅費交通費」という費用項目があります。ここで言う「旅費交通費」とはいわゆる一般用語ではありません。勘定科目としての「旅費交通費勘定」といういわば会計の専門用語としての単語です。
これがどのように違うのか少し見てみましょう。
- 仕事で出張して新幹線の切符代を精算した・・・・「旅費交通費」
- 通勤定期代を支払った・・・・・・・・・・「給与―通勤手当―」
- 客の接待でタクシー代を払った・・・・・・・・・・・「交際費」
- タクシーのチケットをあらかじめ買い置きした・・・・「仮払金」
- 出張のホテル代を支払った・・・・・・・・・・・「旅費交通費」
同じように見える交通に関わる費用であってもその内容によって様々な勘定科目に区分されます。どのような内容であるのかを十分に理解しなくては適切な翻訳にはなりません。
このことは「売上高」であっても「仕入高」であっても同じことがいえます。どのような勘定科目であっても同じことです。
事業体の中では常にモノが動きヒトが動き情報が動いています。これをどのタイミングでどのような金額で、どんな勘定科目で翻訳するのか?これが会計の出発点であり会計の生命線がここにあるといっていいでしょう。
<取引と仕訳の世界>
1、「売上高」をいつ認識し計上するかは常に問題となりやすいところです。
一般に売上高の認識時点は「出荷基準」といわれて製品等が客先に向けて出荷 された時点で「売上高」として計上されます。ただ、例外もあります。
営業部門は当年度の売上高予算があります。どうしてもこれを達成したい時、客先と合意して当社倉庫に在庫したまま客先の了解の基、売上高に計上することもあります。「預かり売上」などとも呼びます。この場合には例外を正当化するべく客先が当該製品を引き取ったとの確認が必要です。従って、客先からの「預け証」の入手、こちらからの「預かり証」の発行などは最低限揃えておく必要があります。
即ち、少なくとも客先が「買った」、こちらが「売った」という証拠を揃えて おく必要があります。
「売上高」という会計の言葉に翻譯するにはその会社で定められた内部手続きをクリアーしなければなりません。この内部手続きを一般に「内部統制制度」といいます。
従って、適切に会計が行われるためには適切な内部統制制度が社内で確立して いることが大前提となります。
公認会計士等が行う会計監査の主な仕事はこの内部統制制度がしっかりしているかどうか?現実に機能しているかどうかを確かめることが大きな仕事となっています。
2、 完成品が出来るまでには様々な工程があります。最終製品となる前に一部の加工工程が必要なことがあります。この際に特定の加工工程を外部に発注する事があります。
A社はいわゆる外注による取引形態です。外注先にある半製品はA社の在庫品であり外注加工に掛かる費用は外注費という製造費用となります。
一方、B社のように半製品を加工先に売却して、加工された品物を改めて購入するという取引形態があります。売却された半製品は相手先に管理責任があるということになります。
A社、B社ともに似かよった加工工程ですが取引形態が異なれば会計も違ってきます。どちらが正しいかではなく、その会社にとってはどちらが管理しやすいかの問題です。
外注という取引形態をとるA社に比べ外注先に移動した半製品を売上高として計上するB社はA社に比べて売上高も仕入高も増加します。
場合によってはB社の場合、「売上高」という数字を求める余り、外注先に半製品を押し込んで「売上高」をかさ上げすることが容易にできるかもしれません。
会計の仕訳は取引形態によっても変わるものです。当然に取引の実態を理解しなければ適切な仕訳は出来ません。
<会計方針と経営方針>
東芝では「不適切」な会計が基で大変なことになっています。トップ経営者が「チャレンジ」と称して無理に売上高を増加させ、結果として数日間で数百億円と言う利益の水増しを行ったという事件です。バイセル取引というそうです。
取引実態が適切とはいえない取引であれば翻訳された会計の世界も当然に不適切となります。
製品在庫を不当に水増しして会計に表現すれば当然に会計は「粉飾決算」となります。こうした操作は最も初歩的な粉飾事例であり、今までに沢山すぎるほどの事例があります。
経済取引そのものが不正な取引であればこれを翻訳した会計の世界も当然に不正なものとなります。翻訳作業がどんなに正しくても経済取引そのものが正しくなければ当然に非難されます。それが会計の辛いところであり会計の限界と言えます。
どんな企業であれ会計ルールの選択は会計方針に左右されます。そして会計方針は結局のところ経営者の経営方針に従わざるを得ないからです。
従って、適切な「仕訳」が出来るためには、適切な会計方針が必要であり、また、そのためには適切な経営方針が前提となる道理です。
<対象をチャンと見ること>
会計の生命は「仕訳」にあると言いました。対象を適切に翻訳し、会計の世界に反映するためには先ず、現実の取引が行われている現場の姿をチャンと見なければなりません。チャンと見るためには現場の人々から素直に聞くことです。先入観なく現場をチャンと見ることです。そのことが出来なければまともな会計は出来ません。
経理を行う人は机に座っているばかりではダメだということです。経理伝票の基となる現場に詳しく精通していなければダメだということです。
絵を描くとき最も注意すべきことは対象をよりチャンと見ることです。自分も昔、習っていた絵の先生から「もっとよく見なさい!」と何度も何度も注意されました。自分ではしっかり見ているつもりでも見えていないことが多いのです。
心の先入観が目の視力を奪ってしまうのかもしれません。
会計の世界でも同じことです。
「人は自分が見たいと思うものしか見ていない」とはローマの英雄カエサルの言葉とされています。
「見る」ということは単純なことですが意外と難しいことなのかもしれません。
<会計は事業の言語である!>
「会計は事業の言語である」といわれます。確かに業種や規模等に関わらず、また、国の如何を問わず、その会社の決算書を見れば会社の事業活動の結果が理解できるからです。それは、決算書が全ての事業に共通する「会計という言語形式」を持つからです。
即ち、会社の膨大な事業取引を会計の言語である「勘定科目」という単語に翻訳し、複式簿記という文法でもって整理統合し、決算書という報告様式で表現します。この意味で会計はビジネス社会の共通言語であるといえます。
ただ、「会計は事業の言語である」との言葉の中身は会計がビジネス社会の共通言語であるという意味だけではありません。
ではどういう意味なのでしょう。
横浜市立大学名誉教授の青柳文司先生は早くから「会計は言語である」との見方で研究されています。「会計」そのものが一種の言語活動であるとの見方によるものです。
その考えの一端を拝借して会計の世界を「記号論」の見方で考えてみます。
<記号と会計>
人間は記号を使用する動物です。記号を通じて考え、記号を見てその次に来る事態を予測し、反応し、準備します。記号によって人間関係を維持し、記号を解釈して人間社会が成り立っています。
現実に札束を見なくても預金通帳の残高を見ておカネの在り高が理解できるわけです。通帳の預金残高は札束を対象とする記号です。更に札束も記号です。これで何が買えるのかが予測できます。
ただ、人間の育った環境、歴史、文化などによって記号を見ての反応、予測、準備の仕方は異なります。記号を解釈する人によって記号に含まれる意味の捉え方が異なるからです。
会計は事業の膨大な取引を勘定科目という会計の言葉に翻譯すると言いました。ここで翻訳された勘定科目は事業取引を記号化したものです。記号化された事業取引が組織的・統一的に整理されて決算書になる訳です。そして事業内外の人々は記号化された事業体の姿を見て何かを予測し、反応します。そこに決算書を巡る人々の阿鼻叫喚の世界があります。
<記号論>
確かに会計を一種の記号活動の一形態と見る見方があります。会計を記号活動として見たらどういうことがいえるのでしょう。
記号に関する研究分野を記号論といいます。
記号論には意味論、構文論、語用論の三つの分野があります。
- 意味論とは記号とその記号が意味する内容に関する研究分野です。会計の世界では「仕訳」の世界がこれに相当します。
- 構文論とは記号と記号の関係に関する研究分野です。記号に働く文法などの世界であり、会計の世界では複式簿記の法則に関する世界です。
- 語用論とは記号とその記号を利用する人間との関連を研究する分野です。会計の世界では決算書とその利用者たちの予測、反応、準備、行動等に関わる世界です。
「会計」を「記号活動の世界」として見ると、会計における「仕訳」及び「複式簿記」並びに「会計を巡る人々」の位置関係がよりよく理解できます。
記号論では意味論の世界が特に発達しています。「意味とは何か?」からスタートです。会計の世界では「仕訳」が出発点となります。
<会計の生命は「仕訳」にある>
会計は「勘定科目」と「金額」という記号で対象を表現します、また、「勘定科目」という単語は限られた数しかありません。膨大な事業取引を限られた数の単語に翻譯しなければなりません。これが会計における「仕訳」の世界です。
会計学の世界は棚卸資産会計、固定資産会計、売上高計上基準、引当金計上基準等々いわゆる会計方法論の勉強が盛んです。大学の授業も会計士試験も会計学の勉強といえばこれらを学ぶことが中心です。これは翻訳すべき対象である企業の出来事をいかに的確に会計という言語に翻譯するかという、いわば翻訳技術の勉強といっていいでしょう。
ただ、会計理論を学んだからといって適切に会計が出来るとはいい切れません。それ以前に、翻譯される対象である事業の取引実態をしっかり理解できていなければ翻訳そのものがおぼつかないでしょう。また、翻訳にあたっての実務慣習などに精通していないと適切な翻訳は困難です。
この意味で会計の生命はいかに適切に生きた「仕訳」が出来るか否かにあるといっていいでしょう。
<「仕訳」の世界>
例えば損益計算書に「旅費交通費」という費用項目があります。ここで言う「旅費交通費」とはいわゆる一般用語ではありません。勘定科目としての「旅費交通費勘定」といういわば会計の専門用語としての単語です。
これがどのように違うのか少し見てみましょう。
- 仕事で出張して新幹線の切符代を精算した・・・・「旅費交通費」
- 通勤定期代を支払った・・・・・・・・・・「給与―通勤手当―」
- 客の接待でタクシー代を払った・・・・・・・・・・・「交際費」
- タクシーのチケットをあらかじめ買い置きした・・・・「仮払金」
- 出張のホテル代を支払った・・・・・・・・・・・「旅費交通費」
同じように見える交通に関わる費用であってもその内容によって様々な勘定科目に区分されます。どのような内容であるのかを十分に理解しなくては適切な翻訳にはなりません。
このことは「売上高」であっても「仕入高」であっても同じことがいえます。どのような勘定科目であっても同じことです。
事業体の中では常にモノが動きヒトが動き情報が動いています。これをどのタイミングでどのような金額で、どんな勘定科目で翻訳するのか?これが会計の出発点であり会計の生命線がここにあるといっていいでしょう。
<取引と仕訳の世界>
1、「売上高」をいつ認識し計上するかは常に問題となりやすいところです。
一般に売上高の認識時点は「出荷基準」といわれて製品等が客先に向けて出荷 された時点で「売上高」として計上されます。ただ、例外もあります。
営業部門は当年度の売上高予算があります。どうしてもこれを達成したい時、客先と合意して当社倉庫に在庫したまま客先の了解の基、売上高に計上することもあります。「預かり売上」などとも呼びます。この場合には例外を正当化するべく客先が当該製品を引き取ったとの確認が必要です。従って、客先からの「預け証」の入手、こちらからの「預かり証」の発行などは最低限揃えておく必要があります。
即ち、少なくとも客先が「買った」、こちらが「売った」という証拠を揃えて おく必要があります。
「売上高」という会計の言葉に翻譯するにはその会社で定められた内部手続きをクリアーしなければなりません。この内部手続きを一般に「内部統制制度」といいます。
従って、適切に会計が行われるためには適切な内部統制制度が社内で確立して いることが大前提となります。
公認会計士等が行う会計監査の主な仕事はこの内部統制制度がしっかりしているかどうか?現実に機能しているかどうかを確かめることが大きな仕事となっています。
2、 完成品が出来るまでには様々な工程があります。最終製品となる前に一部の加工工程が必要なことがあります。この際に特定の加工工程を外部に発注する事があります。
A社はいわゆる外注による取引形態です。外注先にある半製品はA社の在庫品であり外注加工に掛かる費用は外注費という製造費用となります。
一方、B社のように半製品を加工先に売却して、加工された品物を改めて購入するという取引形態があります。売却された半製品は相手先に管理責任があるということになります。
A社、B社ともに似かよった加工工程ですが取引形態が異なれば会計も違ってきます。どちらが正しいかではなく、その会社にとってはどちらが管理しやすいかの問題です。
外注という取引形態をとるA社に比べ外注先に移動した半製品を売上高として計上するB社はA社に比べて売上高も仕入高も増加します。
場合によってはB社の場合、「売上高」という数字を求める余り、外注先に半製品を押し込んで「売上高」をかさ上げすることが容易にできるかもしれません。
会計の仕訳は取引形態によっても変わるものです。当然に取引の実態を理解しなければ適切な仕訳は出来ません。
<会計方針と経営方針>
東芝では「不適切」な会計が基で大変なことになっています。トップ経営者が「チャレンジ」と称して無理に売上高を増加させ、結果として数日間で数百億円と言う利益の水増しを行ったという事件です。バイセル取引というそうです。
取引実態が適切とはいえない取引であれば翻訳された会計の世界も当然に不適切となります。
製品在庫を不当に水増しして会計に表現すれば当然に会計は「粉飾決算」となります。こうした操作は最も初歩的な粉飾事例であり、今までに沢山すぎるほどの事例があります。
経済取引そのものが不正な取引であればこれを翻訳した会計の世界も当然に不正なものとなります。翻訳作業がどんなに正しくても経済取引そのものが正しくなければ当然に非難されます。それが会計の辛いところであり会計の限界と言えます。
どんな企業であれ会計ルールの選択は会計方針に左右されます。そして会計方針は結局のところ経営者の経営方針に従わざるを得ないからです。
従って、適切な「仕訳」が出来るためには、適切な会計方針が必要であり、また、そのためには適切な経営方針が前提となる道理です。
<対象をチャンと見ること>
会計の生命は「仕訳」にあると言いました。対象を適切に翻訳し、会計の世界に反映するためには先ず、現実の取引が行われている現場の姿をチャンと見なければなりません。チャンと見るためには現場の人々から素直に聞くことです。先入観なく現場をチャンと見ることです。そのことが出来なければまともな会計は出来ません。
経理を行う人は机に座っているばかりではダメだということです。経理伝票の基となる現場に詳しく精通していなければダメだということです。
絵を描くとき最も注意すべきことは対象をよりチャンと見ることです。自分も昔、習っていた絵の先生から「もっとよく見なさい!」と何度も何度も注意されました。自分ではしっかり見ているつもりでも見えていないことが多いのです。
心の先入観が目の視力を奪ってしまうのかもしれません。
会計の世界でも同じことです。
「人は自分が見たいと思うものしか見ていない」とはローマの英雄カエサルの言葉とされています。
「見る」ということは単純なことですが意外と難しいことなのかもしれません。
<会計は事業の言語である!>
「会計は事業の言語である」といわれます。確かに業種や規模等に関わらず、また、国の如何を問わず、その会社の決算書を見れば会社の事業活動の結果が理解できるからです。それは、決算書が全ての事業に共通する「会計という言語形式」を持つからです。
即ち、会社の膨大な事業取引を会計の言語である「勘定科目」という単語に翻訳し、複式簿記という文法でもって整理統合し、決算書という報告様式で表現します。この意味で会計はビジネス社会の共通言語であるといえます。
ただ、「会計は事業の言語である」との言葉の中身は会計がビジネス社会の共通言語であるという意味だけではありません。
ではどういう意味なのでしょう。
横浜市立大学名誉教授の青柳文司先生は早くから「会計は言語である」との見方で研究されています。「会計」そのものが一種の言語活動であるとの見方によるものです。
その考えの一端を拝借して会計の世界を「記号論」の見方で考えてみます。
<記号と会計>
人間は記号を使用する動物です。記号を通じて考え、記号を見てその次に来る事態を予測し、反応し、準備します。記号によって人間関係を維持し、記号を解釈して人間社会が成り立っています。
現実に札束を見なくても預金通帳の残高を見ておカネの在り高が理解できるわけです。通帳の預金残高は札束を対象とする記号です。更に札束も記号です。これで何が買えるのかが予測できます。
ただ、人間の育った環境、歴史、文化などによって記号を見ての反応、予測、準備の仕方は異なります。記号を解釈する人によって記号に含まれる意味の捉え方が異なるからです。
会計は事業の膨大な取引を勘定科目という会計の言葉に翻譯すると言いました。ここで翻訳された勘定科目は事業取引を記号化したものです。記号化された事業取引が組織的・統一的に整理されて決算書になる訳です。そして事業内外の人々は記号化された事業体の姿を見て何かを予測し、反応します。そこに決算書を巡る人々の阿鼻叫喚の世界があります。
<記号論>
確かに会計を一種の記号活動の一形態と見る見方があります。会計を記号活動として見たらどういうことがいえるのでしょう。
記号に関する研究分野を記号論といいます。
記号論には意味論、構文論、語用論の三つの分野があります。
- 意味論とは記号とその記号が意味する内容に関する研究分野です。会計の世界では「仕訳」の世界がこれに相当します。
- 構文論とは記号と記号の関係に関する研究分野です。記号に働く文法などの世界であり、会計の世界では複式簿記の法則に関する世界です。
- 語用論とは記号とその記号を利用する人間との関連を研究する分野です。会計の世界では決算書とその利用者たちの予測、反応、準備、行動等に関わる世界です。
「会計」を「記号活動の世界」として見ると、会計における「仕訳」及び「複式簿記」並びに「会計を巡る人々」の位置関係がよりよく理解できます。
記号論では意味論の世界が特に発達しています。「意味とは何か?」からスタートです。会計の世界では「仕訳」が出発点となります。
<会計の生命は「仕訳」にある>
会計は「勘定科目」と「金額」という記号で対象を表現します、また、「勘定科目」という単語は限られた数しかありません。膨大な事業取引を限られた数の単語に翻譯しなければなりません。これが会計における「仕訳」の世界です。
会計学の世界は棚卸資産会計、固定資産会計、売上高計上基準、引当金計上基準等々いわゆる会計方法論の勉強が盛んです。大学の授業も会計士試験も会計学の勉強といえばこれらを学ぶことが中心です。これは翻訳すべき対象である企業の出来事をいかに的確に会計という言語に翻譯するかという、いわば翻訳技術の勉強といっていいでしょう。
ただ、会計理論を学んだからといって適切に会計が出来るとはいい切れません。それ以前に、翻譯される対象である事業の取引実態をしっかり理解できていなければ翻訳そのものがおぼつかないでしょう。また、翻訳にあたっての実務慣習などに精通していないと適切な翻訳は困難です。
この意味で会計の生命はいかに適切に生きた「仕訳」が出来るか否かにあるといっていいでしょう。
<「仕訳」の世界>
例えば損益計算書に「旅費交通費」という費用項目があります。ここで言う「旅費交通費」とはいわゆる一般用語ではありません。勘定科目としての「旅費交通費勘定」といういわば会計の専門用語としての単語です。
これがどのように違うのか少し見てみましょう。
- 仕事で出張して新幹線の切符代を精算した・・・・「旅費交通費」
- 通勤定期代を支払った・・・・・・・・・・「給与―通勤手当―」
- 客の接待でタクシー代を払った・・・・・・・・・・・「交際費」
- タクシーのチケットをあらかじめ買い置きした・・・・「仮払金」
- 出張のホテル代を支払った・・・・・・・・・・・「旅費交通費」
同じように見える交通に関わる費用であってもその内容によって様々な勘定科目に区分されます。どのような内容であるのかを十分に理解しなくては適切な翻訳にはなりません。
このことは「売上高」であっても「仕入高」であっても同じことがいえます。どのような勘定科目であっても同じことです。
事業体の中では常にモノが動きヒトが動き情報が動いています。これをどのタイミングでどのような金額で、どんな勘定科目で翻訳するのか?これが会計の出発点であり会計の生命線がここにあるといっていいでしょう。
<取引と仕訳の世界>
1、「売上高」をいつ認識し計上するかは常に問題となりやすいところです。
一般に売上高の認識時点は「出荷基準」といわれて製品等が客先に向けて出荷 された時点で「売上高」として計上されます。ただ、例外もあります。
営業部門は当年度の売上高予算があります。どうしてもこれを達成したい時、客先と合意して当社倉庫に在庫したまま客先の了解の基、売上高に計上することもあります。「預かり売上」などとも呼びます。この場合には例外を正当化するべく客先が当該製品を引き取ったとの確認が必要です。従って、客先からの「預け証」の入手、こちらからの「預かり証」の発行などは最低限揃えておく必要があります。
即ち、少なくとも客先が「買った」、こちらが「売った」という証拠を揃えて おく必要があります。
「売上高」という会計の言葉に翻譯するにはその会社で定められた内部手続きをクリアーしなければなりません。この内部手続きを一般に「内部統制制度」といいます。
従って、適切に会計が行われるためには適切な内部統制制度が社内で確立して いることが大前提となります。
公認会計士等が行う会計監査の主な仕事はこの内部統制制度がしっかりしているかどうか?現実に機能しているかどうかを確かめることが大きな仕事となっています。
2、 完成品が出来るまでには様々な工程があります。最終製品となる前に一部の加工工程が必要なことがあります。この際に特定の加工工程を外部に発注する事があります。
A社はいわゆる外注による取引形態です。外注先にある半製品はA社の在庫品であり外注加工に掛かる費用は外注費という製造費用となります。
一方、B社のように半製品を加工先に売却して、加工された品物を改めて購入するという取引形態があります。売却された半製品は相手先に管理責任があるということになります。
A社、B社ともに似かよった加工工程ですが取引形態が異なれば会計も違ってきます。どちらが正しいかではなく、その会社にとってはどちらが管理しやすいかの問題です。
外注という取引形態をとるA社に比べ外注先に移動した半製品を売上高として計上するB社はA社に比べて売上高も仕入高も増加します。
場合によってはB社の場合、「売上高」という数字を求める余り、外注先に半製品を押し込んで「売上高」をかさ上げすることが容易にできるかもしれません。
会計の仕訳は取引形態によっても変わるものです。当然に取引の実態を理解しなければ適切な仕訳は出来ません。
<会計方針と経営方針>
東芝では「不適切」な会計が基で大変なことになっています。トップ経営者が「チャレンジ」と称して無理に売上高を増加させ、結果として数日間で数百億円と言う利益の水増しを行ったという事件です。バイセル取引というそうです。
取引実態が適切とはいえない取引であれば翻訳された会計の世界も当然に不適切となります。
製品在庫を不当に水増しして会計に表現すれば当然に会計は「粉飾決算」となります。こうした操作は最も初歩的な粉飾事例であり、今までに沢山すぎるほどの事例があります。
経済取引そのものが不正な取引であればこれを翻訳した会計の世界も当然に不正なものとなります。翻訳作業がどんなに正しくても経済取引そのものが正しくなければ当然に非難されます。それが会計の辛いところであり会計の限界と言えます。
どんな企業であれ会計ルールの選択は会計方針に左右されます。そして会計方針は結局のところ経営者の経営方針に従わざるを得ないからです。
従って、適切な「仕訳」が出来るためには、適切な会計方針が必要であり、また、そのためには適切な経営方針が前提となる道理です。
<対象をチャンと見ること>
会計の生命は「仕訳」にあると言いました。対象を適切に翻訳し、会計の世界に反映するためには先ず、現実の取引が行われている現場の姿をチャンと見なければなりません。チャンと見るためには現場の人々から素直に聞くことです。先入観なく現場をチャンと見ることです。そのことが出来なければまともな会計は出来ません。
経理を行う人は机に座っているばかりではダメだということです。経理伝票の基となる現場に詳しく精通していなければダメだということです。
絵を描くとき最も注意すべきことは対象をよりチャンと見ることです。自分も昔、習っていた絵の先生から「もっとよく見なさい!」と何度も何度も注意されました。自分ではしっかり見ているつもりでも見えていないことが多いのです。
心の先入観が目の視力を奪ってしまうのかもしれません。
会計の世界でも同じことです。
「人は自分が見たいと思うものしか見ていない」とはローマの英雄カエサルの言葉とされています。
「見る」ということは単純なことですが意外と難しいことなのかもしれません。
<会計は事業の言語である!>
「会計は事業の言語である」といわれます。確かに業種や規模等に関わらず、また、国の如何を問わず、その会社の決算書を見れば会社の事業活動の結果が理解できるからです。それは、決算書が全ての事業に共通する「会計という言語形式」を持つからです。
即ち、会社の膨大な事業取引を会計の言語である「勘定科目」という単語に翻訳し、複式簿記という文法でもって整理統合し、決算書という報告様式で表現します。この意味で会計はビジネス社会の共通言語であるといえます。
ただ、「会計は事業の言語である」との言葉の中身は会計がビジネス社会の共通言語であるという意味だけではありません。
ではどういう意味なのでしょう。
横浜市立大学名誉教授の青柳文司先生は早くから「会計は言語である」との見方で研究されています。「会計」そのものが一種の言語活動であるとの見方によるものです。
その考えの一端を拝借して会計の世界を「記号論」の見方で考えてみます。
<記号と会計>
人間は記号を使用する動物です。記号を通じて考え、記号を見てその次に来る事態を予測し、反応し、準備します。記号によって人間関係を維持し、記号を解釈して人間社会が成り立っています。
現実に札束を見なくても預金通帳の残高を見ておカネの在り高が理解できるわけです。通帳の預金残高は札束を対象とする記号です。更に札束も記号です。これで何が買えるのかが予測できます。
ただ、人間の育った環境、歴史、文化などによって記号を見ての反応、予測、準備の仕方は異なります。記号を解釈する人によって記号に含まれる意味の捉え方が異なるからです。
会計は事業の膨大な取引を勘定科目という会計の言葉に翻譯すると言いました。ここで翻訳された勘定科目は事業取引を記号化したものです。記号化された事業取引が組織的・統一的に整理されて決算書になる訳です。そして事業内外の人々は記号化された事業体の姿を見て何かを予測し、反応します。そこに決算書を巡る人々の阿鼻叫喚の世界があります。
<記号論>
確かに会計を一種の記号活動の一形態と見る見方があります。会計を記号活動として見たらどういうことがいえるのでしょう。
記号に関する研究分野を記号論といいます。
記号論には意味論、構文論、語用論の三つの分野があります。
- 意味論とは記号とその記号が意味する内容に関する研究分野です。会計の世界では「仕訳」の世界がこれに相当します。
- 構文論とは記号と記号の関係に関する研究分野です。記号に働く文法などの世界であり、会計の世界では複式簿記の法則に関する世界です。
- 語用論とは記号とその記号を利用する人間との関連を研究する分野です。会計の世界では決算書とその利用者たちの予測、反応、準備、行動等に関わる世界です。
「会計」を「記号活動の世界」として見ると、会計における「仕訳」及び「複式簿記」並びに「会計を巡る人々」の位置関係がよりよく理解できます。
記号論では意味論の世界が特に発達しています。「意味とは何か?」からスタートです。会計の世界では「仕訳」が出発点となります。
<会計の生命は「仕訳」にある>
会計は「勘定科目」と「金額」という記号で対象を表現します、また、「勘定科目」という単語は限られた数しかありません。膨大な事業取引を限られた数の単語に翻譯しなければなりません。これが会計における「仕訳」の世界です。
会計学の世界は棚卸資産会計、固定資産会計、売上高計上基準、引当金計上基準等々いわゆる会計方法論の勉強が盛んです。大学の授業も会計士試験も会計学の勉強といえばこれらを学ぶことが中心です。これは翻訳すべき対象である企業の出来事をいかに的確に会計という言語に翻譯するかという、いわば翻訳技術の勉強といっていいでしょう。
ただ、会計理論を学んだからといって適切に会計が出来るとはいい切れません。それ以前に、翻譯される対象である事業の取引実態をしっかり理解できていなければ翻訳そのものがおぼつかないでしょう。また、翻訳にあたっての実務慣習などに精通していないと適切な翻訳は困難です。
この意味で会計の生命はいかに適切に生きた「仕訳」が出来るか否かにあるといっていいでしょう。
<「仕訳」の世界>
例えば損益計算書に「旅費交通費」という費用項目があります。ここで言う「旅費交通費」とはいわゆる一般用語ではありません。勘定科目としての「旅費交通費勘定」といういわば会計の専門用語としての単語です。
これがどのように違うのか少し見てみましょう。
- 仕事で出張して新幹線の切符代を精算した・・・・「旅費交通費」
- 通勤定期代を支払った・・・・・・・・・・「給与―通勤手当―」
- 客の接待でタクシー代を払った・・・・・・・・・・・「交際費」
- タクシーのチケットをあらかじめ買い置きした・・・・「仮払金」
- 出張のホテル代を支払った・・・・・・・・・・・「旅費交通費」
同じように見える交通に関わる費用であってもその内容によって様々な勘定科目に区分されます。どのような内容であるのかを十分に理解しなくては適切な翻訳にはなりません。
このことは「売上高」であっても「仕入高」であっても同じことがいえます。どのような勘定科目であっても同じことです。
事業体の中では常にモノが動きヒトが動き情報が動いています。これをどのタイミングでどのような金額で、どんな勘定科目で翻訳するのか?これが会計の出発点であり会計の生命線がここにあるといっていいでしょう。
<取引と仕訳の世界>
1、「売上高」をいつ認識し計上するかは常に問題となりやすいところです。
一般に売上高の認識時点は「出荷基準」といわれて製品等が客先に向けて出荷 された時点で「売上高」として計上されます。ただ、例外もあります。
営業部門は当年度の売上高予算があります。どうしてもこれを達成したい時、客先と合意して当社倉庫に在庫したまま客先の了解の基、売上高に計上することもあります。「預かり売上」などとも呼びます。この場合には例外を正当化するべく客先が当該製品を引き取ったとの確認が必要です。従って、客先からの「預け証」の入手、こちらからの「預かり証」の発行などは最低限揃えておく必要があります。
即ち、少なくとも客先が「買った」、こちらが「売った」という証拠を揃えて おく必要があります。
「売上高」という会計の言葉に翻譯するにはその会社で定められた内部手続きをクリアーしなければなりません。この内部手続きを一般に「内部統制制度」といいます。
従って、適切に会計が行われるためには適切な内部統制制度が社内で確立して いることが大前提となります。
公認会計士等が行う会計監査の主な仕事はこの内部統制制度がしっかりしているかどうか?現実に機能しているかどうかを確かめることが大きな仕事となっています。
2、 完成品が出来るまでには様々な工程があります。最終製品となる前に一部の加工工程が必要なことがあります。この際に特定の加工工程を外部に発注する事があります。
A社はいわゆる外注による取引形態です。外注先にある半製品はA社の在庫品であり外注加工に掛かる費用は外注費という製造費用となります。
一方、B社のように半製品を加工先に売却して、加工された品物を改めて購入するという取引形態があります。売却された半製品は相手先に管理責任があるということになります。
A社、B社ともに似かよった加工工程ですが取引形態が異なれば会計も違ってきます。どちらが正しいかではなく、その会社にとってはどちらが管理しやすいかの問題です。
外注という取引形態をとるA社に比べ外注先に移動した半製品を売上高として計上するB社はA社に比べて売上高も仕入高も増加します。
場合によってはB社の場合、「売上高」という数字を求める余り、外注先に半製品を押し込んで「売上高」をかさ上げすることが容易にできるかもしれません。
会計の仕訳は取引形態によっても変わるものです。当然に取引の実態を理解しなければ適切な仕訳は出来ません。
<会計方針と経営方針>
東芝では「不適切」な会計が基で大変なことになっています。トップ経営者が「チャレンジ」と称して無理に売上高を増加させ、結果として数日間で数百億円と言う利益の水増しを行ったという事件です。バイセル取引というそうです。
取引実態が適切とはいえない取引であれば翻訳された会計の世界も当然に不適切となります。
製品在庫を不当に水増しして会計に表現すれば当然に会計は「粉飾決算」となります。こうした操作は最も初歩的な粉飾事例であり、今までに沢山すぎるほどの事例があります。
経済取引そのものが不正な取引であればこれを翻訳した会計の世界も当然に不正なものとなります。翻訳作業がどんなに正しくても経済取引そのものが正しくなければ当然に非難されます。それが会計の辛いところであり会計の限界と言えます。
どんな企業であれ会計ルールの選択は会計方針に左右されます。そして会計方針は結局のところ経営者の経営方針に従わざるを得ないからです。
従って、適切な「仕訳」が出来るためには、適切な会計方針が必要であり、また、そのためには適切な経営方針が前提となる道理です。
<対象をチャンと見ること>
会計の生命は「仕訳」にあると言いました。対象を適切に翻訳し、会計の世界に反映するためには先ず、現実の取引が行われている現場の姿をチャンと見なければなりません。チャンと見るためには現場の人々から素直に聞くことです。先入観なく現場をチャンと見ることです。そのことが出来なければまともな会計は出来ません。
経理を行う人は机に座っているばかりではダメだということです。経理伝票の基となる現場に詳しく精通していなければダメだということです。
絵を描くとき最も注意すべきことは対象をよりチャンと見ることです。自分も昔、習っていた絵の先生から「もっとよく見なさい!」と何度も何度も注意されました。自分ではしっかり見ているつもりでも見えていないことが多いのです。
心の先入観が目の視力を奪ってしまうのかもしれません。
会計の世界でも同じことです。
「人は自分が見たいと思うものしか見ていない」とはローマの英雄カエサルの言葉とされています。
「見る」ということは単純なことですが意外と難しいことなのかもしれません。